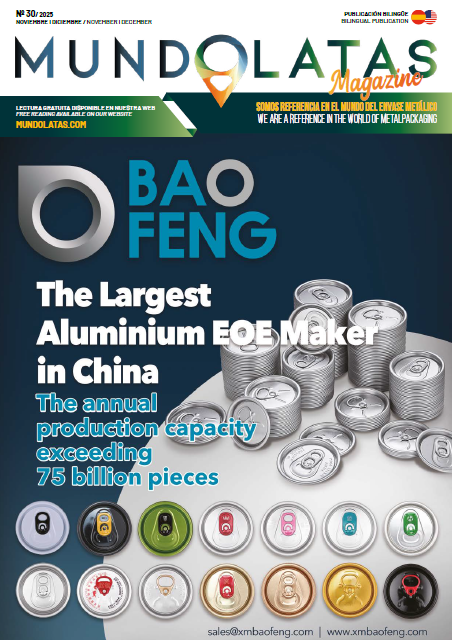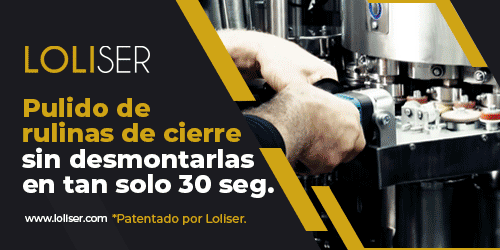グリーンハッシングとは、規制当局、環境保護団体、非営利団体、利害関係者、一般市民からの潜在的な批判を避ける手段として、企業が環境保護活動の進捗状況を報告したり、公表を控えたりすることである。この用語は、ソーシャルメディアや業界イベント、またそれ以外の場でも、パッケージングに関する議論に使われることが増えている。
9月16日に開催されたパッケージング・リサイクル・サミットで、パッケージング・ワールドの編集長マット・レイノルズは、「ブランドは、非難を避けるために、持続可能性への取り組みを難解にしたり、宣伝しなかったりする可能性があり、それは何の役にも立たない」と述べた。「唇は引き締まっている…そしてそれは、獲得したものであれ認識されたものであれ、風評リスクに基づいている。
グリーンハッシングという言葉は、カーボンファイナンスのコンサルタント会社であるサウスポール社が2022年10月に発表した報告書によって注目を浴びるようになった。この報告書では、調査対象となった1,200社のほぼ4分の1が、科学的根拠に基づく排出量削減目標を設定したものの、それを公表する予定がなかったという統計が紹介されている。
今年初め、サウスポールは1,400社を対象とした世界調査の2023年版データを発表し、次のように述べた。 消費財を含む、世界のほぼすべての主要セクターで “グリーンハッシング “の傾向が見られることが初めて確認された」と述べた。消費財を含む。調査対象となった企業の81%が、ネット・ゼロについて発信することは利益につながると回答している一方で、58%は意図的にネット・ゼロに関する社外への発信を減らすことを計画しているという。また、18%は科学的根拠に基づく目標を公表するつもりはないと回答した。
環境に関する主張をめぐって訴訟が起こったり、CPGが2025年までの包装に関する気候変動や持続可能性の目標を達成できなかったり、変更したりしたことに対する批判に直面したりするにつれ、この用語は包装の持続可能性に関する議論にますます登場するようになっている。